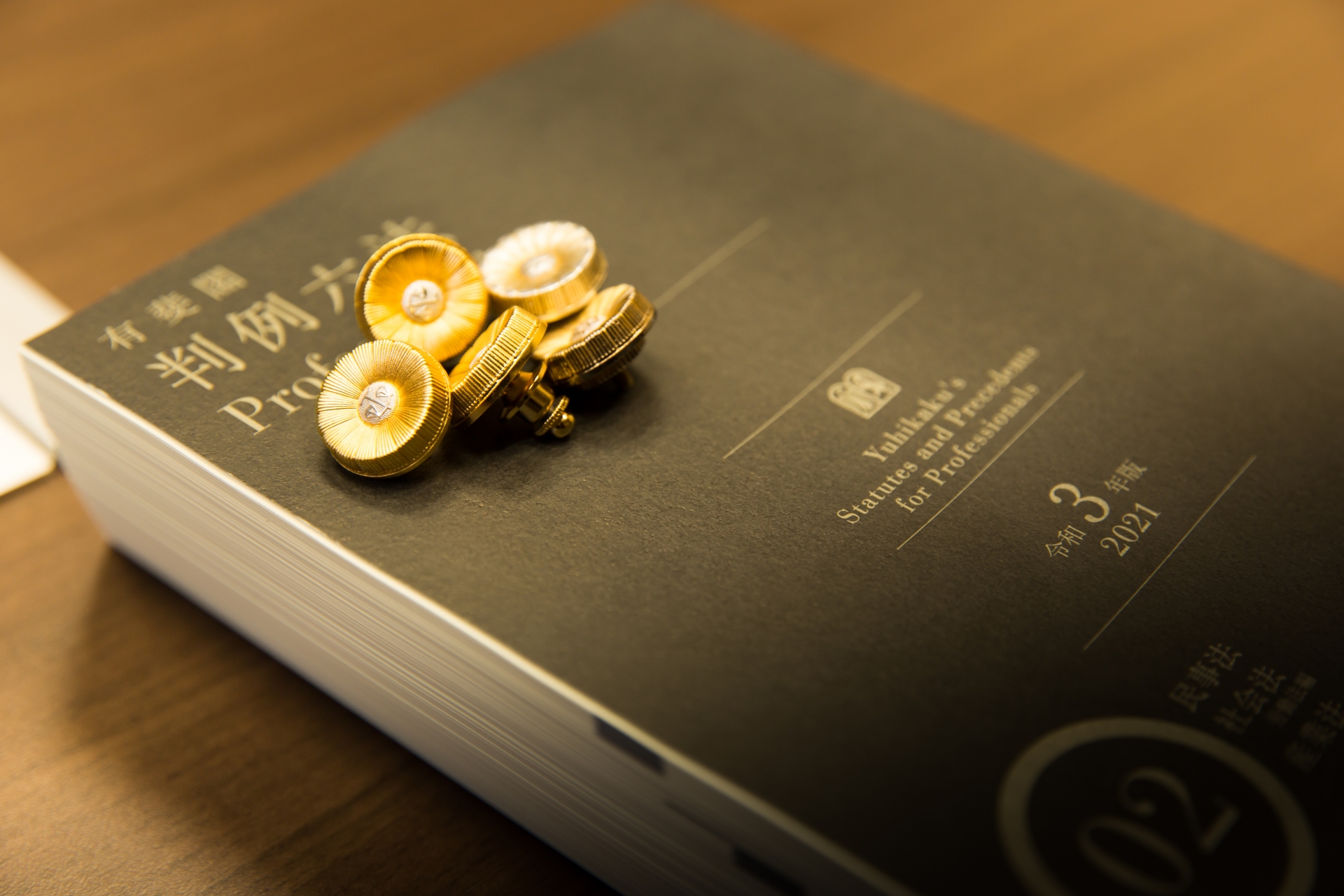
こんにちは!LegalGate講師の小野です。
今回は、私が大学4年のときに勉強を始めてから、1年の留年を経てロースクールに合格し、3年目に予備試験最終合格に至るまでの道のりをお話しします。
失敗もたくさんありましたが、そこから得た学びや気づきも多かったです。同じように司法試験・予備試験に挑戦している方の参考になれば嬉しいです!
目次
【1年目】スタートダッシュの失敗とロー入試の不合
1年目は一言でいうなら「失敗の年」でした。勉強時間もこの後の3年の中では最も少なく、学習効率も悪かった時期だったと思います。
私が勉強を開始したのは大学3年生の終わりごろでした。基礎講座の受講からはじめて、3〜4か月ほどかけて基本7科目を見終わりましたが、今思えば“ただ講義を受けて終わり”の状態でした。何となく判例の名前を覚えたり、こんな論点があるんだといった印象をつかんだだけで、何百時間もの講義の後ではほとんど内容は忘れてしまいました。
その後は予備校の問題集を周回する「作業」に追われました。この時の自分の勉強はまさに「作業」で、とにかく問題を解いて、解説を読んで答えを丸暗記しようとしていました。
部活の引退が4年の12月だったことから、勉強量自体も1日3時間~5時間がいいところで勉強量も足りていませんでした。それでも自分の合格は信じていました。正直、「自分は東大生だから大丈夫だろう」と、どこかに慢心があったのだと思います。
結果としてこの年は予備試験短答、ロー入試(東大、早稲田)すべて不合格でした。点数も合格ラインには程遠く…。東大ローから届いた成績表を見て、自分の実力不足をようやく痛感しました。
そして自分の慢心が恥ずかしく、情けなく思い、来年は必ず受かってやると自分に誓いました。
【2年目前半】ロー浪人開始。個別指導で論文の型を習得する
親と相談して留年が許されたため、2年目は大学を留年、前期は休学し専業受験生となりました。いわゆるロー浪人です。孤独でとてもつらい1年でした。
2年目のはじめ、1年目のロー入試の結果を見て改めて自分の学習の仕方を振り返りました。そこで大学受験当時の自分と比較して以下のような反省点を思い起こしました。
- 勉強時間が圧倒的に足りなかった
- 丸暗記に頼って体系的に理解していなかった
- 論文で何が評価されるかを知らなかった
- 情報がなく、孤独に勉強していた
そして今後これらをどのように修正していくべきかを考え、まず部活の予備合格者の先輩に話を聞きました。そこで勧められたのが個別指導でした。
司法試験の勉強は多くの方が孤独にやっていると思います。ところが一部の大学では(これはロースクールに入ってから知りましたが)大学のゼミ、研究会が充実しており論文指導まで手掛けています。試験から就活の情報までそこで共有しています。そんな人たちと比べ、砂漠と揶揄される東大法学部にいた自分は圧倒的に情報が足りていませんでした。個別指導は私のように環境がない人でも同様の効果を期待できるサービスです。私も先輩から聞いて、ものは試しと思い、Legalgate(主には福田塾長)の受講を開始しました。
ここからすべてが変わりました。
また信頼できる相談相手ができたことも大きかったです。それまでも先輩から参考までに話を聞くこともありましたが、定期的にお話する機会ができたのは精神衛生上よかったと思います。日常の勉強のやり方も気になることをなんでも聞くことができましたし、受験の情報(予備試験の相場感、各科目のレベル感など)も格段に知りやすくなりました。私の弱点は以上の経緯から個別指導の受講を開始して自然と解消されていきました。
また日常の論文学習も体系化されて行きました。それまでの自分は論証を覚えることに必死でしたが、個別指導の中でそれは論文の1側面に過ぎないことを痛感しました。論文で評価される事項は問題提起、規範、あてはめはもちろん、個々の文章の読みやすさまで多岐にわたります。単語レベルで表現に気を配る必要があるというのは自分では絶対に気づけなかったと思います。
こうして勉強開始1年目の頃よりは勉強時間も格段に増え順調にロー浪人生活はすすんでいたと思います。
【2年目後半】予備短答に惨敗とロー入試での逆転
そんなこんなで順調に来ていた浪人生活でしたが、7月に待ったがかかります。予備試験の短答に大差で落ちてしまったのです。
ここまで、短答の勉強については書いていませんでしたが、もちろん対策は重ねていました。肢別本を3周はしており一般教養も十分に点が取れていました。しかしながら法律科目は、またしても肢別本を「作業」のようにこなしており、知識の一元化もできておらず、過去問形式での演習も足りていませんでした。点数の流動性が高い公法科目などで模試などは点を稼いでいましたが、本番では軒並み下振れしました。民法刑法といった安定してとるべき科目も点数が取れていないなど、科目ごとの勉強の区別もできていなかったのです。これらの勉強上の問題点も試験の自己採点まで気づくことができず、前年のロー入試以上の悔しい結果となりました。
この結果にかなり焦りました。2浪は避けたかったので、もともとの受験予定を練り直し、受験校を増やしました。最終的に中央、慶応、早稲田、東大と4校を受験することにしました。
勉強も過去問を手に入る分は全ての学校のものを起案し、とにかく演習を重ねました。この過去問演習こそ、実力が大きく伸びた要因のひとつだと思います。
それまでは予備試験の対策のなかで多論点の予備過去問を混乱しながら解いていました。予備校の問題集も繰り返しやっていましたが、過去の「作業」によって答えを覚えてしまっていました。
しかし、基本的な問題が多いロースクールの過去問を多くやったことで基本論点への理解が深まり、初見の問題の起案にも相当慣れてきました。短答までに個別指導で論文答案の指針を身に着けることができていたことも起案を促進しました。個別指導も並行して行うことで各科目の論文の型を身に着けることができました。
そして7,8,9月と連続して試験を受けて知識の安定感も増しました。毎月大きな試験を受けることで、毎回その直前に内容を復習し、このころは論証の暗記レベルも高まっていました。私大が一通り終わった後はのんびりと下四法のブラッシュアップを重ね、憲民刑の論証もあてはめの手順までより正確に覚えることができました。
結果として受験した中央、慶応、早稲田、東大と全てから合格をいただくことができました。特に、時には予備試験合格者も落ちることがあるという東大ローに受かることができたのは自信につながりました。
勉強開始2年目は実力の伸びが結果にも結び付き、うまくできた1年だったと思います。
特に、
- 個別指導により勉強、受験の情報量が増えたこと
- 論文の型を身に着けることができたこと
- 短答不合格によりロー入試にむけて全力で過去問に取り組めたこと
は勝因になったと思います。
【ロー合格後】少し休んでから再始動。予備への再挑戦。
ロー入試が11月に終わりそこから予備試験の出願がある2月までは正直勉強はしていませんでした。1年間専業受験生をやり、精神的にとても疲弊していました。そこで大学で残していた単位を回収しつつ、友達と飲んだり、海外旅行に行ったりと遊んでいました。(今思えば、ローに入学すると司法試験を受けるまで心が完全に安らぐ時がなくなるので、この時たくさん遊んでおいてよかったと思います。)
大学の期末が終わり、予備試験の出願をした2月ごろに勉強も再開しました。予備試験については受けることに迷いはありませんでした。ちょうど私の1つ上の学年から在学中受験が始まり、予備試験に受かっても司法試験の受験年度は変わらない可能性が高かったことからロー勢は予備試験をうけなくなるという説が当時ありました。(現に入学後予備試験の勉強をしていた人達は思っていたより少なかった印象です。)しかし、就活に有利になるという説もありましたし、何より2回落ちた試験を(まだ1回受ける機会があるのに!)あきらめるということが私には絶対にできませんでした。
それまでの勉強の反省を踏まえて
- ロー入学前:判例学習
- 入学後:短答対策
という流れで勉強することにしました。
判例学習について、私は初学者の段階ではそんなにしなくていいと思っています。正直判例を読むのって退屈ですし、初学者の段階で読んでも何が重要なのかよくわかりません。ですが、ある程度勉強が進み、自分の論文に落とし込むことができれば判例は最良のインプット教材になります。司法試験も予備試験も結局判例がベースになっている問題が多いためです。
この時の私は、論文の型を学んできたことで、判例を読んでそこで得た知識を自分の論文に落とし込むことができるようになっていました。そこで予備校の判例講座を購入し、それをベースに基本七科目の判例知識を身に着けていきました。2~3月にのんびり受講を開始し、受講が終わったのは6月くらいでしたが、この判例学習を通して大きく論文知識がついたと思います。
短答は去年2年間の反省からしっかり対策をしようと決めていましたし、短答さえ突破できれば論文は受かる自信がありました。そこで教材は短パフェと択一六法に選びなおし、短パフェを周回して知識を択一六法に一元化してそれを覚える、というメジャーな学習法(いわゆる武蔵理論)にすることにしました。時期は4月から着手して5-6月に短期決戦でやると決めました。
*よくSNSではどの問題集がいいとか、短パフェはオーバーワークだとかいう話が話題になりますが、個人的には短パフェが一番いいと思います。短答が苦手な人は短パフェでとにかく量でカバーするしかないと思っていましたし、今でも自分はそれでよかったと思います。
【3年目春~初夏】ローと予備、地獄の両立生活
ここからはローの勉強と予備試験の勉強をいかに両立したか、又はできていなかったかを書いていきたいと思います。
率直にいってローの勉強と予備試験の勉強の両立は相当きついです。
ロースクールによるとは思いますが、私が通っていたロースクールは試験対策という色は薄く科目によって論文、短答に直結するかしないかが授業によって大きく分かれていました。多くは親和性が高くなく、短答は全く違うことを勉強していると言っていいほどでした。しかもローではソクラテスメソッドを採用しており、何回かに一回は確定であたるため予習が不可欠です。極めつけに、予備短答の数日後にローの期末が始まるといった鬼畜日程でもありました。
ロー入学後2週間くらいして両立が相当きついと気づき、私は短答が苦手だということも加味して勉強スタイルを調整しました。
まず論文に役に立ちそうな科目は予習から復習までやり、そうではない科目は自分が当たる回だけ予習しそれ以外は内職をすると決めました。また授業は落単のぎりぎりのラインまで授業を休みました(特に直前期)。あまり褒められたものではないですが、自分の短答の実力からしてここまでしてようやく戦えると思っていました。
5~7月は論文学習は全てストップし、短答に全振りしました。問題を解いて知識をまとめる武蔵理論を実践しました。
結果、短答は自己採点160点後半でした。毎回得点源になっていた一般教養が下振れしたこと、公法科目で被害が想定以上だったことなどが原因でした。それでも開示は170点代で辛くも短答突破を果たしました。
受かった喜びよりも、基本7科目短答という地獄をもうしなくていいという安堵の方が大きかったです。
ちなみに期末試験は短答後に大急ぎで詰めて極めて平均的な成績を取ることができました。
【3年目夏~秋】予備試験論文へ。選択・実務科目の強化
短答突破後は少し気持ちが楽になりリラックスして勉強ができました。2年間私を阻んだ短答は突破し短答コンプレックスが緩和しましたし、論文に落ちたとしても翌年ロー在学中受験ができそうだという安心感もありました。
夏休みはそれまで対策ができていなかった実務科目と選択科目に力を入れました。いずれもそれまでにも2~3年分は過去問をやっていましたが、基本7科目ほどの成熟度には至っていませんでした。対策はこれまでと変わらず過去問演習でしたが、基本7科目で論文の型を身に着けた後となってはただの暗記ゲームと化していました。(逆に分析本と答案をくらべてもそれで合格水準に達したと感じました。)
また要件事実の勉強は民法に直結する、ということを肌で感じ理解できたのもこの時でした。事実認定も勉強し、リーガルマインドが身についてきたなと思っていました。
基本7科目は残った過去問を片付け、判例学習に終始し、予備校の講座を何回も繰り返し聞いて理解を深めました。
そして迎えた予備試験論文当日。最初で最後のこの舞台に緊張するどころか、どこまで戦えるかというのが楽しみでさえありました。
試験は過酷でした。民実の問題形式が変わっていたり、行政法が3年?4年?連続の原告適格出してきたり、憲法の問題が意味わからなかったり、色々ありました。試験時間も長く、最後の民事系の試験時間では頭はそんなに動いていないのに手は動いているといった不思議な感覚に陥るなどの体験もしました。
それでも繰り返し本番と同じタイムスケジュールで演習していたため、基本的には耐えることができました。現場思考の必要がでてくるのも想定内で、対処手順を決めていたので相対的に書き負けることがなかったと思います。結果として大けがを負う科目もなく全科目無難に終えることができました。
そして3か月後の12月、無事に合格の発表を見ることができました。
論文式試験を振り返ると
- 論文の型を身に着けていた
- 判例学習を進めていた
- 演習を繰り返し予想外の設問にも対応できた
この3つが主な勝因だったと、以上の経験から思います。
*余談ですがロー生は予備試験論文直後にサマークラークという弁護士事務所のインターンに行く人が多いです。私も論文の次の日からインターンラッシュで、夏休みはあっという間に終わり、10月からは秋授業で全く休まる暇はありませんでした。
3年目予備試験口述~ロー期末
論文に受かり地獄が終わるかと思いきや、ここからが最大の地獄でした。というのも口述の3日前から期末が始まる予定でした。
口述前後の一週間は期末、休み、期末、期末、口述、口述、期末…といった具合でした。しかも90%以上が受かるという前情報と俺ならいけるといういつもの謎の自信から口述対策はそこまでやっておらず(過去問10年分くらいは読んでいました)、期末の勉強に重きを置いていました。ところが口述の2週間前に先輩と練習をしたところ、不合格レベルの出来で、焦って対策を開始しました。
口述の対策としては、大島本と基本刑法各論を頭に叩き込み、とにかく声をだして各種定義を丸暗記しました。口述前日の期末は切ることにして、前日、当日の午前中、1日目の試験後は頭をフル回転させて暗記に勤しみました。
試験は緊張もしていましたが、直前まで暗記することだけを考えていて集中していました。口述試験当日は発射台と言われる第1待機室と試験直前の第2待機室があり、第2待機室ギリギリまで暗記をすることができます。私は暗記の過程で作成した、要件事実、刑法各論定義メモをひたすら見返していました。試験中は試験官の声に全力で耳を傾けました。
ちなみに口述試験はロー勢が有利だと思います。日常的にソクラテスメソッドで教授に指導されて(詰められて?)いますし、裁判官から要件事実を教わる授業もあり、私見ですが口述はローでの授業がとてもいきたと思います。
そこから期末を乗り越え無事口述試験に合格し、予備試験最終合格を果たしました。
3年間のまとめ
以上、3年間を軽くその勉強のスタイルと共に振り返ってみました。1年目を除いて概ねうまくやれていたとは思います。ですがやはり最初のインプットを論文の型の勉強と併せてやるなどすればもっと効率よくできたのは確実です。また個別指導は2年目だけ受講していましたが、学習効率の点からいってもむしろ最初に受講すべきだったと思います。
ロー在学中受験、CBT方式の登場により司法試験制度自体が大きく変革期にあるのは間違いありません。それでもこの法律の試験の苦しさはだれしも司法試験合格までに経験すると思います。私の失敗と成功体験がみなさまの参考になれば幸いです。
